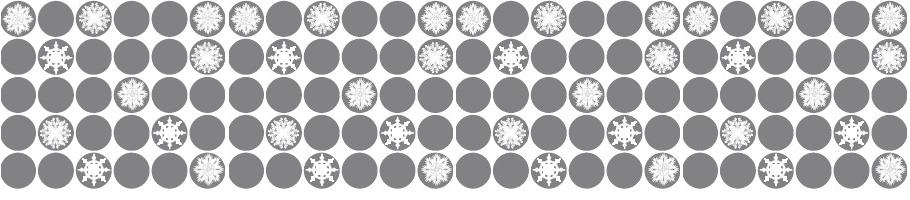川越せんべい店
南部煎餅(なんぶせんべい)
※以下、ウィキペディアより抜粋
小麦粉を原料にしたせんべいの一種。
八戸南部氏が藩主家だった旧八戸藩地域に伝承の焼成煎餅である。
由来 [編集]
その由来には諸説あるものの、大方は「長慶天皇創始説」を取っている。
長慶天皇創始説
南北朝時代の頃、南朝の長慶天皇が名久井岳の麓(現・三戸郡南部町)、長谷寺を訪れ、食事に困った時に家臣の赤松助左衛門が近くの農家からそば粉とごまを手に入れ、自分の鉄兜を鍋の代わりにして焼き上げたものを天皇に食事として出した。この食べ物が後の南部せんべいの始まりであるとする説である。
さらに天皇はその風味を非常に好んで度々、赤松に作らせ、天皇は煎餅に赤松氏の家紋「三階松」と南朝の忠臣、楠木正成の家紋「菊水」の印を焼きいれることを許したという。現在の南部煎餅には確かに「菊水」と「三階松」の紋所が刻まれている。昭和20年代初頭に、八戸煎餅組合によって「南部せんべい」の創始起源の再整理が行われた際、この説を中心に整理された。
八戸南部氏創始説
応永十八年(1411)の「秋田戦争」で八戸軍(根城南部)の兵士たちが戦場でそば粉にごまと塩を混ぜ鉄兜で焼いて食べたところ、将兵の士気大いに上がり、戦勝することができた。その後多くの合戦に携行され、南部せんべいの始まりとなったとする、「八戸南部氏創始」説もある。
キリスト創始伝承
昭和十年頃に新郷村の盆踊り「ナニャドヤラ」から、突如誕生した新郷村の「イエス・キリスト日本渡来伝説」と共に沸いた話の一つ。ゴルゴタの丘での処刑を逃れたキリストは、シベリア経由で日本に渡来した。八戸の八太郎に上陸して新郷村の沢口や迷ヶ平で生活したという。この時キリストの郷里で食べていたパン(マッツァー)に似せて作り食べていた食べ物が、現在の南部せんべいの始まりであるという説である。
歴史 [編集]元々は八戸藩で作られた非常食である。現在は青森県と隣接する岩手県にまたがる地域、そして北海道にも存在する。
旧弘前藩側の地域では津軽煎餅・八戸煎餅とも呼ぶ。これは青森県西側に位置した弘前藩初代藩主・津軽為信は元々主南部家の家臣であり、南部家の領土の一部を後の弘前藩として独立した為、南部家中の風習がそのまま残った事に由来する。
なお南部煎餅という名前は巖手屋が商標登録しているため、他の煎餅屋が販売する際には別の名称を用いている。
なお(株)小松製菓が「南部せんべい物語」「南部せんべい茶屋」で商標登録しているが、「南部せんべい」で商標登録に至った例は、今のところ無い。
| 川越せんべい店 | ||
|---|---|---|
青森県上北群おいらせ町 |
||
TEL 現在工事中です |
||
川越せんべいについて 川越せんべい商品 南部煎餅の由来 南部煎餅について |